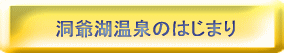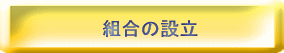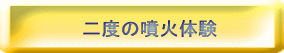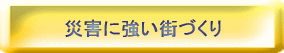|
|
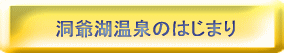
|
|
 |
|
|
| 北海道南西部の洞爺湖をを中心とした地域は洞爺湖・有珠山・昭和新山など自然美を有する『火山と湖と温泉』のある北海道有数のリゾート地として広く知られています。洞爺湖温泉は明治43年、有珠山の寄生火山である四十三山(よそみやま)の噴火活動により誕生した温泉とされています。火山国・温泉国といわれる日本でもその誕生の時期や生成の原因と過程が明らかな温泉は極めて稀です。その後、大正6年に温泉宿が開業し、これが洞爺湖温泉のはじまりとされています。 |
|
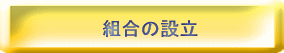
|
|
 |
| たくさんの温泉宿が開業し、観光地として脚光を浴び始めると街は急速な発展を遂げました。昭和23年の洞爺湖温泉観光協会の設立、翌24年には支笏洞爺国立公園の指定により宿泊施設や土産店、飲食店も年を追うごとにその数を増していきました。しかし、街の発展に伴う温泉源の増加により泉温はしだいに低下し、源泉の個人管理に限界を感じ始めた街の有志たちの働きかけにより昭和35年9月に『洞爺湖温泉利用協同組合』が設立しました。 |
|
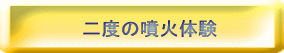
|
|
 |
 |
| 昭和52年8月、平成12年3月と当組合も設立以来、二度にわたり噴火を体験しました。特に平成12年の噴火は記憶にも新しく噴火口が温泉街の間近と言うこともあり源泉や配湯管に多大なダメージを被りました。地殻変動による配湯管の折損は20箇所にもおよび、最も噴火口に近かった2源泉(洞爺8号源泉・Hー3号源泉)ではケーシングパイプの断裂と管理小屋の崩壊により使用不能となりました。幸い宿泊施設の営業再開時には応急的ではありますが配湯が可能になりました。しかし、源泉の減少による湯量不足は当時最も頭を抱える問題でした。 |
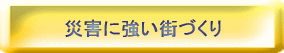
|
|
|
 |
| 国や道、そして全国のみなさまの心温まるご支援により使用不能となった源泉の代替を新たに2本掘削し、懸念されていた繁忙期の湯量不足も解消されました。また、今回の災害での経験を生かし地殻変動の著しかった箇所には約24m毎に可とう伸縮継手を設置し、次回の噴火では配管設備の被害を最小限に抑えることが可能となりました。さらに、洞爺湖温泉は温泉揚湯による温泉源の水位変動が少ない為、これまで観測していなかった水位の変動も新たに監視項目に加えることにより、いち早く火山活動の前兆を見極められるようになりました。こうした一連の施設整備を行うことで火山との共存をはかり、自然の恩恵である温泉の有効利用に努めることが私達の使命であると考えています。 |